学校薬剤師の仕事の1つに、生徒たちに対して学校保健に関わる教育をすることがあります。クラス単位での授業をする場合や、学校全体での教育に関わる場合もあります。
学校保健
「学校保健とは、学校において、児童生徒等の健康の保持増進を図ること、集団教育としての学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、自己や他者の健康の保持増進を図ることができるような能力を育成することなど学校における保健管理と保健教育」(文科省HP 学校保健の推進)とされています。
保健管理
学校の環境衛生、健康診断、健康相談、感染予防
保健教育
(1)保健学習
学習指導要領により決められた学習。心身の発育・発達、健康、生活習慣病、環境などの内容が含まれます。
(2)保健指導
学級活動や運動会などの授業外の場における指導。
保健学習における教育項目
医薬品の適正使用
医薬品への正しい知識を持って、正しく使うことで薬の効果をきちんと得ることや不適切な使用による健康被害を防ぎます。
飲酒、喫煙、薬物乱用防止
身体に大きな影響を及ぼすアルコール、タバコ、覚せい剤や違法薬物などの危険性を知識として教える必要があります。
生活習慣病
食事、睡眠、運動など生活の仕方で病気の原因となるなど健康に影響を及ぼすことを教えます。
環境教育
教室の換気の必要性や照明、カーテンなどの利用方法など適切な環境が健康や学習環境に影響があることを教えます。
アンチ・ドーピング教育
高校生になるとトップレベルの競技者として国体などのドーピング検査対象の大会に出場する生徒もいます。そのような生徒も含めて、小学生、中学生からもドーピング防止についての知識を持ってほしいと考えています。オリンピックなどの大きな大会があると話題になることも多く、医薬品の適正使用という観点からも学校教育の中で伝える必要があります。

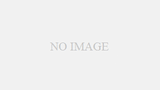
コメント